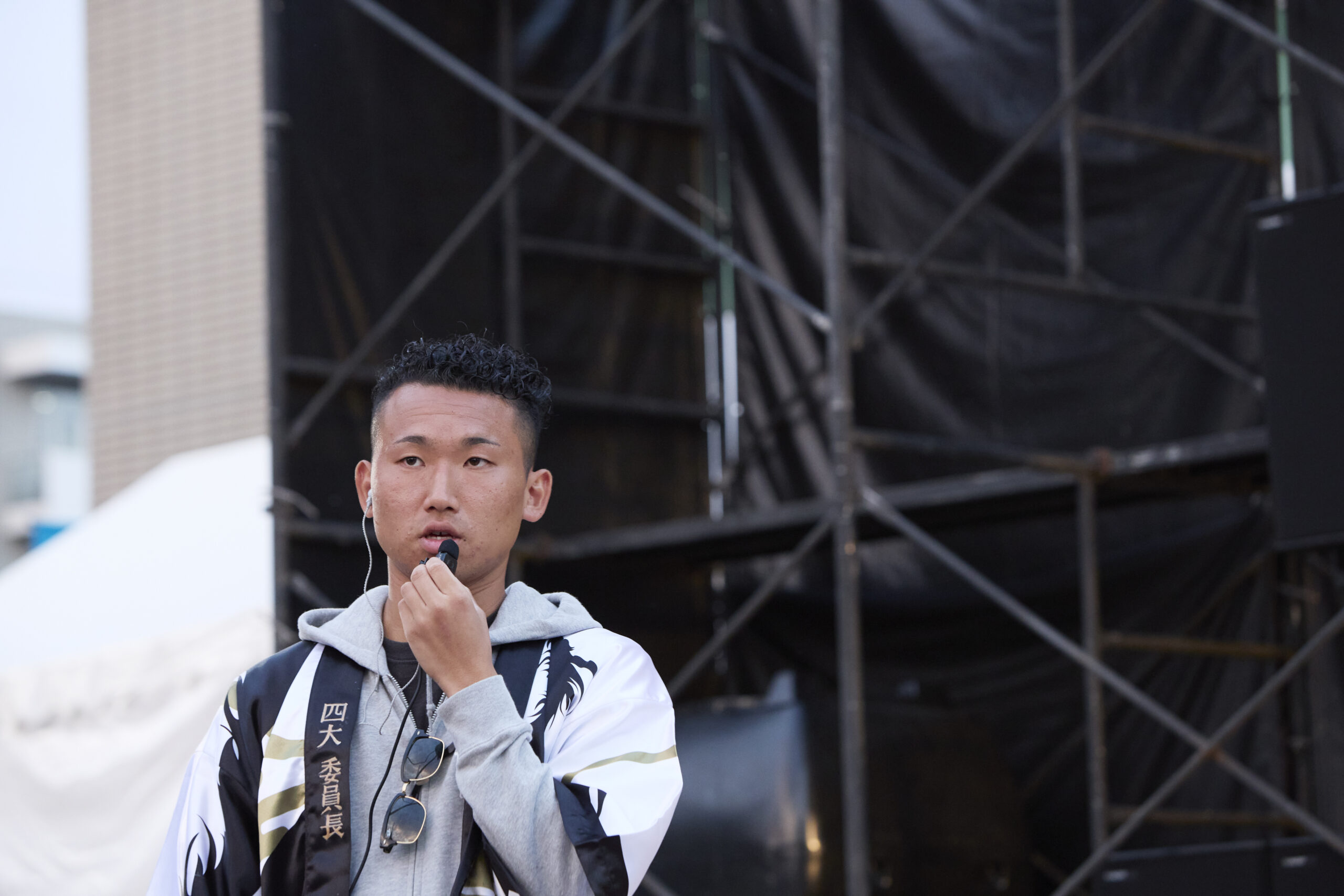Shitennoji University
- 人
感性を育み、未来をつくる―音楽教育の可能性|教育学部 矢倉 瞳先生インタビュー

子どもの「音による表現」を中心に、幼児教育・学校教育を教える矢倉先生。音楽教育を学ぶようになったきっかけ、自らが音と関わる体験から始める学びや、教育学部で4年かけて保育を学ぶメリット、そして音楽教育の可能性などについてお話を伺いました。
学校音楽教育の意義とは?から研究が始まった
もともと自分の演奏技術や表現力を身につけるため器楽専攻で学んでいたのですが、大学4年生のとき、学校で音楽を学ぶ意義が十分に理解されず、音楽科の授業時間が減っていることを知りました。また、「みんな音楽家になるわけじゃないのに、なぜ音楽の授業って必要なの?」と知り合いに聞かれたとき、自分でも明確に答えられませんでした。そこから、大学院で音楽教育を学ぶ道を選び、音楽表現が人の成長にどう関わるのかについて研究をはじめました。大学院では哲学をベースとして学んだのですが、毎日目から鱗のような学びの連続でした。例えば哲学者のジョン・デューイは、音楽や芸術を日常と切り離された特別なものとはせず、日常生活の中で感性やイマジネーションの働きによって生まれるものであると言っています。人の経験の一部として芸術があるという考え方は、音楽表現を学んでいく上でとても大切なベースになっています。

体験から学ぶ音楽教育
私の授業は、学生に一方的に知識や技能を伝えるのではなく、学生が実際に体験したことを基盤に、それをリフレクションしながら学びを深めていくことを大切にしています。そのため、まずは音を鳴らす・遊ぶなど誰もが参加できる活動から始め、後に振り返りを行い、その活動の意味を考えるようにしています。よく、初回の授業で「ピアノが弾けないんです」「歌が苦手なんです」と不安に思う学生がいるのですが、本来子どもの表現は、子ども自身がもっている衝動や興味、そして感性等によって繰り広げられるものであり、特別な技能は必要ありません。「技能的なことが大切なのではなく、自分自身の興味や感性、イマジネーションを大切にしながら幼児の音楽教育に関わっていくことが大事」と伝えています。


輪ゴムと箱や、身の回りのものを使って音楽を作る授業では、花火や虫の鳴き声を表現したものが出てきたり、大阪出身の学生からだんじりのリズムによる表現が出てくることもあります。私が想定しなかった表現がたくさん出てくることもあり、実際に人が表現をする姿を見ることができるのは、私自身もすごく勉強になりますし、教材の力、学生たちの力がすごいなと思っています。

「いい保育者とは何か?」を4年でじっくり考える
幼児教育保育コースでは、免許・資格を取得することだけを目的とするのではなく、4年間の中で「いい保育者とは何か?」「自分の保育観とは?」を問い続け、じっくり掘り下げて考えることができます。そうした考える姿勢や自分の保育観をもつことは、卒業後、現場で直面するさまざまな課題に主体的かつ柔軟に対応する力へとつながると思います。4年間を見ていると学生たちの成長ぶりもすごいです。1年生の頃と比べたら4年生でもう別人かというぐらい成長し、授業の中での発言も立派になっていきます。その成長に何らかの形で関われているのは嬉しいですし、子どもが幸せに生きられる社会の実現に、教育を通じて携われること、それが教員として何よりのやりがいです。

芸術教育でAIにはない感性を磨いていく
平和で民主的な社会の実現には教育が重要な役割を担っていると考えます。なかでも芸術教育は、AIにはない人間の本質ともいえる情緒やイマジネーション、感性を育む点で、今後ますます意義を深めていくと思います。実は最近は短歌に興味があるのですが、短歌に触れて思うことは、日々感じたことや経験を短歌にできる術を持っていれば、人生がさらに豊かになるだろうなということです。世の中にあふれる激しい言葉もすべて短歌として昇華できれば、もう少しやさしい世の中になるんじゃないでしょうか。短歌を例にしましたが、短歌だけでなく、音楽、造形、ダンスといった芸術的な経験は人の営みの中で生まれ、人の生を豊かにしてくれるものだと思います。だからこそ、音楽教育に携わるいち教育者として、自分にできることをこれからも精一杯実践していきたいと思います。

- WRITER
- 矢倉 瞳 / やぐら ひとみ
教育学部 教育学科 専任講師
担当講義:教育専門演習ⅠⅡ、教育専門研究ⅠⅡ、音楽への扉、保育内容の理論と方法(表現活動・音楽)、音楽実践演習(器楽・弾き歌い)、幼児と表現ⅠⅡ、教育基礎演習ⅠⅡ、インターンシップⅠ、子ども学概論、教職実践演習(教諭)、教科内容論(音楽)
研究分野:音楽教育、教育実践学
人間の本質ともいえる「感性」の育成を目指し、幼児の内側(思いやイメージ)と外側(音)の相互作用の連続がみられるような音楽表現のための具体的な方法を探究しています。
- 関連リンク
- 四天王寺大学:教育学部 教育学科